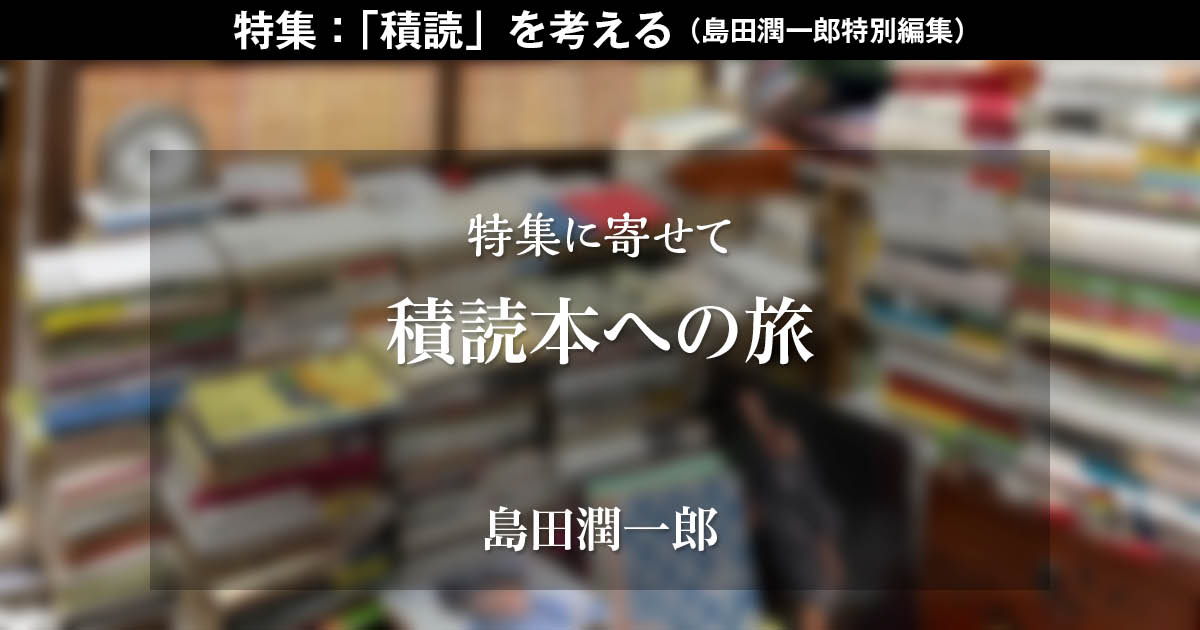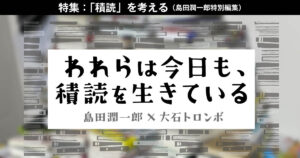島田潤一郎
その本をいつ買ったのか、もはや覚えていない。新刊で買ったのか、古本で買ったのか、どの書店で買い求めたのか、全部、記憶からなくなってしまって、その本そのものだけがある。30年以上、ずっと。
おそらく『三国志』からの興味で手にとったはずだから、中学生のころであるのには間違いない。当時、ミステリー小説や歴史小説を自分のお小遣いですこしずつ買うようになり、新潮文庫や講談社文庫などが自室の小さな書棚に年々増えていった。けれど、岩波文庫だけはいつまでも経っても、その1冊だけだった。
それだけではすこしさびしいから、高校3年生のときに、同じ岩波文庫の青い背の、福沢諭吉の『学問のすゝめ』を買った。それからずいぶんと長いあいだ、『学問のすゝめ』と、そして『論語』が「つがい」のようにぼくの書棚に並んだ。
どちらの本も買ってから一度も開いていなかった。読んでみようともまったく思わないのだった。でも、捨てようとか、だれかにあげようとも思わなかった。間違いなく内容のある本だし、いつか読むときが来るだろうと信じていた。
こういう本が典型的な「積読本」であり、ぼくの書棚にはそういう「積読本」が2、300冊ある。
もちろん、そうでない「積読本」もあるのだ。それらは話題だったから買ったとか、古本で安かったから買ったとか、古本なのにやけに状態がいいから買ったとか、友人にもらったとか、いろいろな理由で部屋のあちこちに積まれることになったのだが、共通しているのは、いまの自分からはずいぶんと遠いところにあるということだ。それはもちろん、物理的にではなく、心的にである。
いってみれば、買った当時は、「読みたい度」が100なのだ。それが翌日には97ぐらいになって、翌週ぐらいには85ぐらいになっている。翌月はみるみるうちに70ぐらいになっていて、こうなるともはや、そんなに遠くない遠距離恋愛ぐらいの距離である。
東京からいうと高崎ぐらいだろうか。
あるいは、浜松ぐらいだろうか。
いずれにせよ、まあまあ遠い。でも、まだ気合いひとつでなんとかなるくらいの距離でもある。
けれど、1年も放っておくと、気合いだけではとてもではないが、その本を手にとることができない。計画を立てなければならない。
年末年始に読もう。ゴールデンウィークに読もう。あるいは、来月の2泊3日の出張のときにでももっていこう、と思う。
でも、いざその日の朝になると、そんな古い本を読みたい気分にはならない。代わりについ最近買った本をかばんにつめ、その「積読本」に何度目かの謝罪の言葉をつげる。ごめんね。
では、これらの「積読本」は永遠に積まれたまま、ぼくの部屋で眠り続けるのかというと、そうではない。
ひとつに、「神の手」のようなものがある。ある日突然、友人が、ぼくの部屋にある「積読本」について話し出し、「昨日読み終わったんだけど、あれはすごくいい本だな」という。ぼくは友人に、積んだまま読んでいないとは打ち明けることができず、「あれはほんといい本だよね」と返す。その晩、ぼくは買ってから10年ぶりにその本を開き、初めて最初の1行を読む。こうした「神の手」は、SNSの時代になって、格段にその登場機会が増えた。
海外のプロサッカー選手がステップアップの移籍を果たすとき、紋切り型のように、「次の列車はもうやってこない。だから、(あらたなチーム行きへの)列車に飛び乗ったんだ」と話すが、彼らが話すとおり、その「積読本」と向き合う「神の手」がふたたびぼくの前に現れる保証なんていうのはどこにもない。だから、「積読本」を読む機会が目の前に現れたら、必ずそのときに読まなければならない。
もうひとつは、「呼び水」としての読書だ。1冊の本を読み終わると、その本と関連するなにか違う本を読みたくなる。そのこころの働きを利用して、長年の「積読本」と向き合う。そのためには、ときにあらたな本を買い求める必要があるが、「積読本」を減らすためなのだから、それは致し方のないことだと思う。
すべての本は違う本へと繋がる、豊かな水脈を持つ。
ぼくがいま読んでいる本もまた、何十、何百の読書のリレーを経て、岩波文庫の『論語』へときっとつながっていくはずなのだ。
しまだ・じゅんいちろう
1976年高知生まれ、東京育ち。日本大学卒業後、派遣社員やアルバイトをしながら放浪。2002年に出版社「夏葉社」起業する。『長い読書』(みすず書房)、『電車のなかで本を読む』(青春出版社)など著作多数。