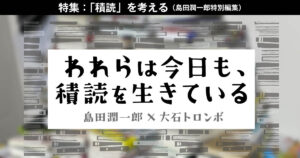文学紹介者
頭木弘樹
私の蔵書のほとんどは積ん読である。
ひと部屋を埋めつくすだけではすまず、別の部屋や廊下などあちこちに乱立する本棚、そこからはみ出してさらに積み上げられた本の山。
「これ、ぜんぶ読んだの?」と妻から聞かれたとき、私は少しためらってから、「ほとんど読んでない」と正直に答えた。
「一生かかっても読めないよね?」
「そうだね」
「じゃあ、読むものだけ選んで、あとは処分したら?」
たいへんもっともな意見だが、そうはいかないのだ。
「どれを読むか、わからないんだよ」
「これは確実に読みそうとか、これは読まなそうとか、あるんじゃない?」
「人生、何があるかわからないから、この先、自分が何を読みたくなるかわからないんだよ」
たしか、クローネンバーグの映画だったと思うが、ある人物の膨大な数のビデオが置いてある図書館のような施設が出てきた。何か悩んだときに、そこに行けば、もう死んでいるその人物に相談できるのだ。ビデオの数が膨大なので、どんな相談でもそれに対応するビデオが必ずあるのだ。
そのビデオと同じでことで、相談しそうなものだけにビデオを減らしてしまったら、なんにもならないのだ。新たな悩みができれば、読みたい本も変わってくる。
その理屈だと、それこそ図書館くらい本がないといけないことになるが、さすがにそれは無理だ。だから、これでもずいぶん制限しているのだ。本当はぜんぜん足りないけど、スペースとお金の都合で、泣く泣く我慢しているのだ。
「じゃあ、図書館を利用すれば?」
図書館に住むのは、たしかにひとつの夢だが、読みたい本が近くの図書館には置いてないことも少なくない。また、置いてあったとしても、本は手元に置いておいて、何度もめくってみたりすることが大切なのだ。あるいは、ふと思い出したときに、本棚から出してきて開きたいのだ。
「読みたいときに買えばいいんじゃないの?」
これももっともだ。でも、読みたいときには、もう絶版ということがほとんどなのだ。しかも古書は高騰していることが多い。読みたいときに本はなし。さりとて古書を買うお金もなしだ。
私は本を読み始めたときに、この「絶版」と「古書の高騰」にずいぶん苦しめられた。私はもともとは本を読むほうではなく、20歳で難病になったときから本を読むようになった。まずカフカから読むようになったのだが、その数年前に『決定版カフカ全集』全12巻が新潮社から出ていた。ところが、日記や手紙の巻はもう品切れで新本では手に入らなかった。入院していたので、いろんな古書店に往復ハガキを出して問い合わせた(まだインターネットは普及していなかった)。その手間とハガキ代だけでもかなりかかった。なかなか見つからず、見つかっても手が出ない値段だったりした。
筒井康隆のアンソロジーや『みだれ撃ち瀆書ノート』でも、いろんな作家や作品を知った。それらの本を買おうとすると、これがまたほとんど絶版だった。ル・クレジオ『巨人たち』、ロブ=グリエ『新しい小説のために』、『ハロルド・ピンター全集』……どれもこれも、なかなか見つからない。『ハロルド・ピンター全集』など、全3巻を集めるまで、どれほど苦労したか。
本というのは、なんでこんなにすぐに絶版になるんだ!古本はどうしてこんなに高くなるんだ!というのが本を読み出したときの、私の大いなる不満だった。私は本と、そういう出合い方をしたのだ。
その後も、新刊で出た本の購入を「高いなあ」などと迷っていると、そのすきに絶版になって、もっと高い古書になってしまうことが何度もあった。これでは、すぐに買って積んでおくようにするしか、しかたがないではないか。
ただ、この苦い経験のおかげで、けっこう儲けたりもした。どういうことかと言うと、すぐに絶版になって古書が高騰しそうな本は2冊買っておくのだ。そうして、絶版になったら、1冊は古書店に売るのだ。そうすると、新刊で買ったときより、かなり高く売れる。しかも、これは出版社や著者にとっても少しでも売れ行きが増して嬉しいし、古書店も嬉しいし、絶版になった本を探している過去の私のような人間にとっても嬉しい。誰もが嬉しくて、儲かるのだから、みなさんにもぜひオススメしたい。もっとも、しばらく置いておくスペースを必要とするのと、その本の価値をわかってくれて、その本をほしがるようなお客のついている古書店に売らないといけない。ブックオフなどの新古書店に持ち込んだのでは、ただ損をするだけだ。
というわけで、私の蔵書は、最初のうち、絶版と古書の高騰に対する恐怖から増えていった。しかし、ある程度、積ん読が増えてくると、別のよさにも気づくようになってきた。
ふと、突然、「こういうふうなものを読みたい」と思うことがある。悲しいことがあって、せつない本を読みたいとか。そういうとき、すぐに手元にあるのである。そして、それを抱くようにして、転がって読むことができるのである。
こういうとき、書店に行って、いろいろ探して、買ってきて、それから読むというのは、ちょっとちがう。そういう能動的な気分ではないのだ。たまたま手元にないといけないのだ。しかも、すでに過去に自分が厳選した、自分好みのものが。
断捨離系の片づけのアドバイスに「1年間、まったく必要なかったものは捨てる」というようなのがあったが、私の場合は、これはまったくあてはまらない。10年くらい、手をつけず、思い出しもしなかった本が、ある日、突然必要になって、とても大切な本になったりする。
だから、私は積ん読は大切だと思っている。体力で言えば余力にあたる。ぎりぎりの体力だけでは生きていくのに危険だ。余力が必要だ。あるいは、積ん読は非常食のようなものだと思う。不意に必要になり、そこから買おうとしても無理だったりする。積ん読があれば、しばらく保つのだ。
絶望の中で読書を始めた私は、本は命綱だと思っている。順調に楽しく生きているときには、本なんか読まなくても大丈夫だ。でも、いざ何かあったとき、挫折とか、不幸とか、絶望とか、そういうときには、本はとても大切なものだ。とくに文学。たくさんの物語を読むことによって、壊れて混乱してしまった自分の人生の物語を、あらためて書き直すことができる。
とはいえ、もちろん積ん読のマイナス面もある。なにしろ、読んでいないので、持っているのを忘れることがある。そして、また買ってしまうのだ。トランプの神経衰弱が得意な妻は、そういう本のダブりを見つけるのもうまく、同じ本が2冊をあるのをよく見つける。科学が好きな妻は「これが物質と反物質なら、対消滅で両方消えるところだよ」と言って、両方を処分しようとしたりする。同じ本が3冊出てくると、さすがに私も反省する。
また、本が山積みになっていると、持っているはずの本がどこにあるかわからなくなる。あるいは、ひっぱり出せなくなる。仕事で引用したいのに、「どこかに必ずあるはずなんだけど」と何時間も捜索したりすることになる。じつに無駄な時間だ。
あるとき、こういう経験もした。目を病んで、本が読めなくなったのだ。これには愕然とした。家の中に山ほどある本が、すべて無用の長物、紙クズになってしまったのだ。そのとき、電子書籍なら、文字をものすごく拡大できるので、なんとか読むことができた。
それ以来、目が治った後も、電子書籍を買うようにしている。自分の本もなるべく電子書籍化してもらっている。場所もとらないし、二重に買うこともないし、検索すればすぐに出てくるし、本文の検索もできるし、他のメリットも多い。
自炊にも挑戦した。本をバラして、カットして、スキャナーで読み込んでPDF化するのだ。これもとてもいいと思った。ただ、装幀も好きな本は、そういうわけにいかない。また、画面で読むのと、紙で読むのはやはりちがうから、これは紙で読みたいという本も多い。
というわけで、積ん読の山はなかなか減らせないままだ。なんとかしなければと思うが、まだ読んでいない本たちの背表紙のタイトルや著者名を見るだけで、ずいぶん幸せなのだ。

かしらぎ・ひろき 20歳で潰瘍性大腸炎を発病。長い闘病生活中にカフカの言葉が救いとなった経験から、2011年『絶望名人カフカの人生論』(飛鳥新社)を編訳する。『口の立つやつが勝つってことでいいのか』(青土社)、『自分疲れ ココロとカラダのあいだ』(創元社)など著作多数。