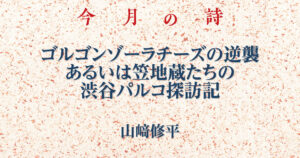詩に宿る命の光
マーサ・ナカムラ
親戚の女性には、5歳になる娘がいる。
彼女がクローゼットの整理をしていた時、自分の結婚式の二次会用に購入したエメラルドグリーンのワンピースを見つけて、懐かしく眺めていた。すると5歳の娘が、「これママが着ているのを見たことがある」と言い出した。
このワンピースを着たのは、結婚式当日の一度きりだった。しかもそれはその子が生まれる前のことで、見たはずがないと諭すと、彼女は「神様と一緒に、この緑のワンピースを着たママを見た」と言ったのだった。その日が結婚式当日であったことも言い当てた。
それから、まるで堰を切ったように、生まれる前の記憶らしきものを語り始めた。彼女は生まれる前、神様とたくさんの子どもたちと一緒に、「きれいなお城」に住んでいた。毎日お城の天井掃除と皿洗いに奮闘していたら、ある日神様からその功績を認められて、「ママの子ども」として選ばれた。そしてたくさんの子どもたちをお城に留守番させたまま、神様と二人だけで外出して、ママをこっそりと見物しに行ったとか。そのときに、結婚式の様子も見ていたらしい。
子どもは雲の上から、自分の親を選んで生まれてくるという話は私も聞いたことがあった。その子が住んでいたという「きれいなお城」に思いを馳せる一方で、そこに今も暮らしている「たくさんの子どもたち」のことを考えずにはいられなかった。
詩集『風の領分』(岸田将幸/書肆子午線)に収録された本作品「月明かり」(次ページ)にある、「生まれていない者がすべて生まれますように」という一行に行き当たったときに、私はこの「きれいなお城」に残されたというたくさんの子どもたちのことを思い出した。
この詩は、単なる親子愛をうたった詩ではない。もっと大きな、人間愛をうたっている。「親が我が子を愛する」ではなく、一つの命の持ち主として、生まれてくる命、生まれてこなかった命、これから生まれてくる命といった、あらゆる命の形を愛する詩である。手を伸ばせば触れられる距離にある命、地に沈んでいった命、空に浮かんでいる命を思ううちに、いつしか、その大きな愛は自分の命にさえ向けられる。
この詩を読んだ後に、現代詩文庫『岸田将幸詩集』(思潮社)を読むと、作風の違いに驚くかもしれない。現代詩文庫は、詩人の初期の作品から近年の作品まで、代表作を採録したオムニバス形式になっている。今回取り上げた最新詩集『風の領分』は2021年に刊行されており、2013年刊行の『岸田将幸詩集』に本作品「月明かり」は収録されていない。
初期の作品は、肉体をもって生まれてきたがゆえの苦しみを激烈に描いている。生の先には必ず死があるが、死への扉は肉体を引き剥がす非常な苦しみをもって開くほかないという死生観が表れているように思う。第1詩集『生まれないために』が刊行されたのは2004年。最新詩集『風の領分』を開くと、そこにはやはり死生観がある。しかし、初期の作品とは異なり、生と死は天国と地獄のような正反対の世界ではなく、生者の世界の上に静かに死者の世界があるような、平行の世界観を感じる。
今年2024年は岸田将幸さんにとって、第1詩集刊行から20年目の年にあたる。初期の作品から最新詩集まで追っていくと、一人の詩人から、ここまで幅広い作風が生まれることに驚く。時の移り変わりとともに、人が変わらずにはおれないように、詩人から生まれる詩も、このように自然に変わっていくものなのかもしれない。それでも私は、岸田さんほど詩の空気が自然な形で変化していく詩人を見たことがないような気がする。
詩論、エッセイ、農業日記(新聞記者から2017年にアスパラガス農家へと転身されている)をまとめた『詩の地面 詩の空』(2019年刊行/5柳書院)のあとがきには、次のような1節がある。
落ち着いて、机の前に座る時間はさほどない。何か思いつめたとき、車のハンドルや膝の上を急ごしらえの机とし、しかし宛先もなく文字を記す時間は極めて心許なく感じた。だが、このような場所で書かれるわずかな言葉を、まずは自分が全面的に信頼し『詩の地面』としなければならない。
変遷していく自分の「地面」と、胸に宿る命の「光」。目には見えない自分の強さを信じ続けることは難しいが、いま確かに目の前にある、「地面」と「光」を見失わずにあれば、どんな暗い道だって歩ける。自分に宿る光が見えなくなったとき、このような詩があれば、どれだけ心強いだろう。私はこの詩に出会って、問答無用に生きる方へと人の背中を押す詩は、命に似た輝きを帯びていることを知ったのだ。

マーサ・ナカムラ●1990年埼玉県生まれ。詩人。第54回現代詩手帖賞受賞。『狸の匣』(思潮社)で第23回中原中也賞、『雨をよぶ灯台』(思潮社)で第28回萩原朔太郎賞受賞。
次ページに、岸田将幸さん作『月明かり』を全文掲載しています