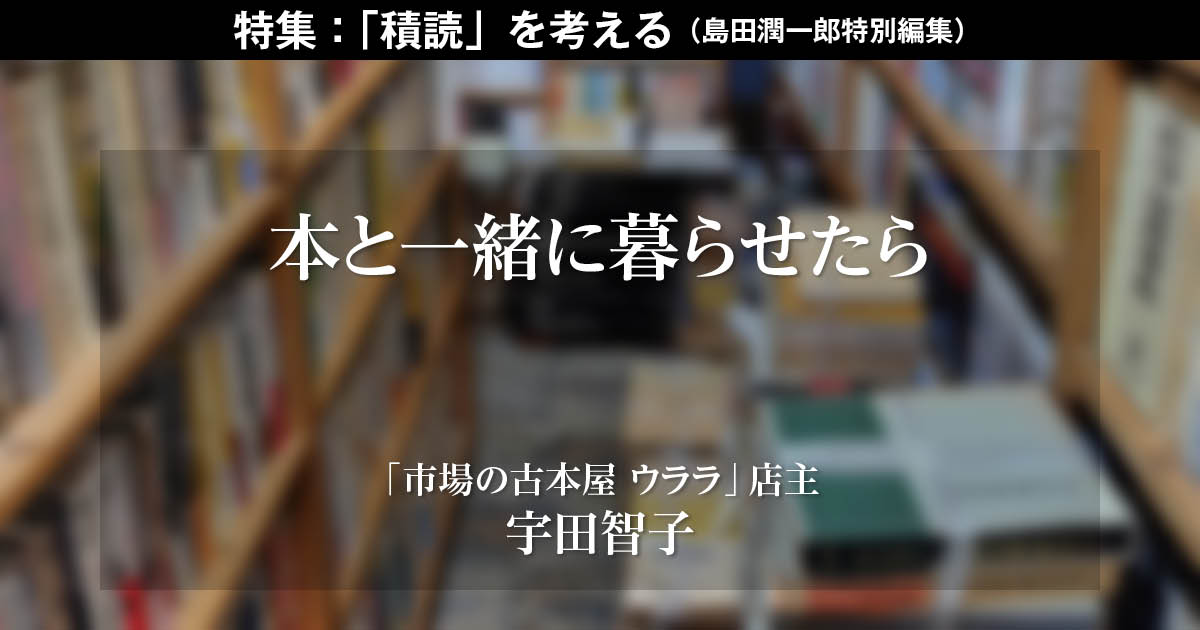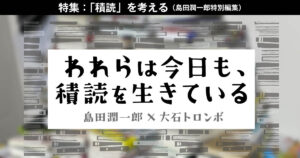「市場の古本屋 ウララ」店主
宇田智子
古本屋に来るお客さんに「まだ読んでいない本が家に積んであるので、それを読み終えたら買いにきます」と言われて、びっくりすることがある。積んだ本を読み終えるまで買わないの? 積んだ本を読み終える日なんて、来るの?
私は部屋に積んだ本のほとんどを読んでいない。それがふつうなので、わざわざ「積ん読」と呼ぶことはない。いつか読み終えるとも思っていない。
子どものころは、部屋に読んでいない本があるなんて考えられなかった。本が足りなくて、どの本もくり返し読んでいた。読みきれなくなったのは大学生のころから。それまでは目についた本を読むだけだったのが、講義のたびにたくさんの本を紹介されるようになり、読まなければいけない本が増えた。しかも読むのに時間のかかる本ばかり。読みたい本を積みあげたまま、読まなければいけない本を読む苦しみも知った。
卒業後は新刊書店に就職して、そびえ立つ棚のまえで途方にくれた。棚の上から下まで見ても、知っている本すら1冊もない。どれから読めばいいのか迷っているそばから、次々に新刊が入ってくる。ブックガイドを買ったり、書店員向けのマニュアルを読んだりしながらも、安易に本を知ろうとしている自分に罪悪感を覚えた。「あらすじを読んでもその作品を読んだことにはなりません」と、文学部の先生がいつも言っていたのに。
でも私は研究者ではない。結局、書店で働くうえでなによりも勉強になったのは、棚に本を並べることと、お客さんからの問い合わせに答えることだった。
毎日、棚に補充する本が山のように入荷してくる。仕分けした本を抱えて棚のまえに立ち、並ぶ本の背表紙を眺める。フッサールは左上、その下にメルロ=ポンティ、隣にハイデガー、続いてアーレント。棚に本を入れながら、哲学史の流れを体で覚えた。
新刊が入ってくると、タイトルと著者と出版社を見る。帯を読む。著者略歴と目次を読む。そのうちになんとなく似た本を思いだして、その隣に置く。
お客さんからの問い合わせを受けて本を探すときは、棚の本の背表紙をひたすら読む。あるはずの場所になかったら、ほかにありそうな棚を想像して移動し、また背表紙を読む。見覚えのある本が増えると背表紙を速く読めるようになり、本を見つけるのも速くなる。
本を棚に並べるために、棚の本を探すために、書店員は日々、何百もの本の背表紙を眺めて、読んでいる。その数は、どんな研究者にも読書家にもきっと負けない。本とこんなふうにかかわるのもありだと思うようになった。
やがて私は那覇の商店街で古本屋を始めた。数分で棚を全部見わたせるくらいの小さな店だ。店先に座っていると、ときどきお客さんからこんな声を聞く。「実は、本は苦手なんだ」「買っても最後まで読めないの」。それまで勤めていた新刊書店には、なんの疑いもなく本を買う人ばかりがいて、だれもそんなことは言わなかった。
古本屋になってから、本を買う人、読む人の姿がよく見えるようになった。店に私しかいないので、すべてのお客さんに自分で接する。会計のとき、どうしてこの本を買ったのか話してくれる人もいる。前にここで買った本の感想を伝えてくれる人もいる。
お客さんともっとも密にかかわるのは、本の買取のときだ。店に本を持ってきてもらうか、本の冊数が多ければ、私がご自宅にうかがう。ある家はすべての部屋に本棚があり、廊下と階段にも本が積まれ、本を詰めた収納ケースがベランダに積み上げられていた(ケースを開けたら、本はカビで真っ黒になっていた)。ある家は庭に書庫としてプレハブが立っていた。ある家はクローゼットに掛けられた背広の下まで本が積まれていた。
こういう家では、運んでも運んでも本が減らない。床が抜けそうなほどの重さ、一生かけても読みきれないページの厚さ。それだけの本を積み上げておいて、さらに買いつづける。いったいどういう心境なのか。ひとりの人が買う本の数に限りはないのか。
そうして集めてきた本を手放すお客さんの様子はさまざまだ。すっきりした顔をしている人。未練がましく「やっぱりこれだけ残そうかなあ」と本に手を伸ばしている人。亡くなったご家族の蔵書を処分して、「これで安心しました」と泣いている人もいた。
買い取った本を店に運び、手入れしながらぱらぱらとめくってみる。ページが折られたり線が引かれたりしていると、「やばい」と思う。あの人は折ったり書きこんだりする人なんだ。ほかの本にも書きこみがある可能性が高いから、注意して確認しないといけない。ある人から分厚い歴史書を何十冊も買い取ったときは、どの本も最後まで書きこみがされていて感心した。ちゃんと通読したのだなあ。
反対に、買い取った本に読んだ形跡がないことも多い。「読んでないからきれいでしょう」と誇らしげに言われたりする。先日、買取に行った建築事務所には、『BRUTUS』や『Pen』といったさまざまな雑誌の建築特集の号が数十冊積まれていた。きっとまめに書店に通って、平台をチェックしていたのだろう。「買って満足して読まなかった」と建築家は笑っていた。興味のある雑誌を見つけて買う、それだけでじゅうぶん楽しかったのかもしれない。
『読んでいない本について堂々と語る方法』(ピエール・バイヤール著、大浦康介訳、ちくま学芸文庫)という本がある。文庫化されたのが2016年で、いま私の手元にあるのは2020年の第11刷。めちゃくちゃ売れているようだ。タイトルにひかれる人がたくさんいるのだろう。
最初に「略号一覧」が示される。「〈未〉ぜんぜん読んだことのない本」とか、「〈忘〉読んだことはあるが忘れてしまった本」とか。〈忘〉ね、と笑いかけて気がついた。いや、前にもここを読んだはずなのに忘れていた!まさに〈忘〉だ。
私は2013年の年明けに、この本の単行本を那覇の球陽堂書房で買った。店の入口の近くの、人文系出版社の本を集めた棚で目にとまり、自分へのお年玉のつもりで買った。家に帰って、畳に寝そべって読んだ。著者はまじめなのか開き直っているのか、ちっとも読んでいないくせに「堂々と」していておかしかった。
いま10年以上ぶりにめくってみると、ところどころ見覚えがあるような、ないような。私はこの本を最後まで読んだのだろうか。読んだとしても覚えていないのなら、読んでいないのと同じだ。それでいて、この本について何度か語ったことがある。内容は忘れていても、買った店や、読んだときの気分は覚えている。単行本は手放して(自分の店で売った)、今回この原稿を書くときに思いだして、文庫を買いなおした。
「積ん読」という言葉がしっくりこないのは、そもそも「読んだ」=「積ん読ではない」と自信をもって言える本がないからだ。同じところだけ何度も読みかえす本。あとがきだけ読んだ本。部屋にあっていつもタイトルと著者名を見ている本。買ったことを忘れている本。本屋で何度も手にとっては棚に戻す本。図書館で借りて読めないまま返す本。本とのかかわり方は無数にあって、どこから「読んだ」と言えるのかわからない。
古本屋は、だれかが本屋で買って家に置いていた本を買い取って、次の人に売る仕事だ。古本屋に売られるまでにじっくり読まれた本も、何十年も触れられずにいた本も、持ち主がいなくなったあと何年も積まれたままの本もある。本と人のかかわりを目の当たりにしていると、本とは自由につきあえばいいのだと思えてくる。本をほんとうに読み終えることはないし、どんな本ともいつかは別れなければいけないのだから。
大事なのは読んだか読んでいないかではなくて、本がそこにあること。家になくても、本屋で見たり、図書館にあるのを知っていたりするのもいい。どこにも在庫がなくて探しつづけるのも、電子書籍で買うのもいい。自分で1冊ずつ集めた本を積んで、ごはんを食べながら背表紙を眺めたり、掃除のために持ち上げてまた積んだりして、一緒に暮らせたら最高にいい。
読めなくて困っているお客さんには、どんどん本を見て触ってほしいと伝えたい。読んでいない本を積んだままで、また買ってもいい。おそれずに本にかかわってくれたらと思う。

1980年神奈川県生まれ。2002年ジュンク堂書店に入社。池袋本店で人文書を担当した後、2009年那覇店開店に伴い異動。2011年に退職し、同年、那覇市の第1牧志公設市場の向かいに「市場の古本屋 ウララ」を開店する。 著書に『すこし広くなった 「那覇の市場で古本屋」それから』(ボーダーインク)、『本屋になりたい この島の本を売る 増補』(ちくま文庫)などがある